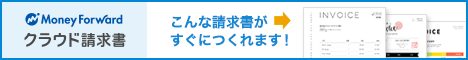今回は、節税について。
特にフリーランス、個人事業主の人は必見です。
仕事で、
・よく領収書に収入印紙を貼ることがある
・収入印紙を貼るような契約書を交わすことがある
といったケースがあれば、
収入印紙代を節約できる(印紙税を節税できる)方法をご紹介します!
今回はわかりやすく「領収書」にフォーカスして説明していきますが、契約書など領収書と同様に収入印紙を貼る必要のある印紙税の課税文書であれば、同じく適用される方法ですので、ぜひご確認ください。
みなさんはご存知でしたか?
「PDFなどの電子データで作成した領収書であれば、金額が5万円以上だとしても収入印紙を貼らなくても問題ない」
という事実を。
「いやいや、5万円以上の領収書は200円の収入印紙を貼って渡さないとダメでしょ」
という認識の人が多いはず。
私も最近までそうでした。
特に飲食業の仕事では、手書きの領収書を発行して収入印紙を貼るケースは非常に多いですし、デザインなどの仕事の場合でもお客様から領収書の発行をお願いされて収入印紙を貼った領収書を渡す、といったことも日常茶飯事。
これが、収入印紙を貼らずに済んだら、1枚200円だとしてもチリも積もれば・・ということで、
たいした手間もかからず、節税(印紙税を払わずに済む)できると知って、今回国税庁のwebサイトを中心に調べた結果をまとめたいと思います。
普段、仕事で領収書に収入印紙を貼っている方でも、収入印紙のこと、印紙税のこと、収入印紙を貼る必要のある課税文書のこと、などほとんど知らなかったり、意識しないまま、「5万円以上の領収書には収入印紙を貼る」といったルールだけ覚えている方も多いと思いますので、
今回の説明の前提となる、「収入印紙とは」、「領収書とは」、といった説明から順にいきたいと思います。
基礎知識は知ってるから、「PDFなどの電子データで作成した領収書であれば、金額が5万円以上だとしても収入印紙を貼らなくても問題なし」の根拠や情報源だけ知りたい!という方は、記事の後半へお進みください。
領収書、領収書に貼る収入印紙の基礎知識を理解する
そもそも収入印紙ってなに?
収入印紙とは、「印紙税」という税金を納めるための方法の1つです。
「印紙税」とは、日常の経済取引において、作成される契約書や金銭の受取書(領収書)などの「課税文書」を作成した時に課税される税金のこと。
例えば、
お客様から5万円の売上代金を受け取った際に発行する領収書には、200円の印紙税が課税される対象となります。
その場合、200円の収入印紙をコンビニなどで購入して(間接的に印紙税を納付したことになる)、領収書に貼って渡すことで、印紙税を払ったとみなされるわけです。
つまり、
5万円以上の領収書などの「課税文書」を作成した時には収入印紙で「印紙税」を納めないといけません。
印紙税を納めなかったときの罰則
ちなみに、収入印紙を貼り忘れた、収入印紙を貼らないといけないことを知らなかった、収入印紙の金額を間違えて少なく貼ってしまった、など、結果的に印紙税を規定どおり納めなかった時、税務署の調査で発覚した際には、
当初に納付すべき印紙税の3倍に相当する額を払わなければいけません。
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。 引用)国税庁webサイト「 No.7131 印紙税を納めなかったとき 」
自主的に気づいて申し出たときは1.1倍に軽減されるとのこと。
どちらにせよ、無知なばかりに多く税金を払わなければいけなくなってしまうので、気をつけたいですね。
逆に、印紙税を払いすぎていたことに気づいた場合は還付請求もできます。
詳しくは国税庁webサイト「No.7130 誤って納付した印紙税の還付」を。
印紙税について、もっと詳しく知りたい方は、国税庁webサイトの「印紙税の手引き(平成29年5月)」をご確認ください。かなり詳しく説明が載っています。
レジのレシートも領収書。領収書の定義を確認
ここでは、領収書の定義を確認しておきましょう。
領収書は印紙税の中では、「金銭または有価証券の受取書(第17号文書」に該当する課税文書と定義されています。
国税庁webサイトでは以下のように説明があります。
金銭の「受取書」、「領収証」、「領収書」、「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらに、お買上票などと称するもので、その作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証するものであるときは、ここにいう金銭または有価証券の受取書に該当します。 引用)国税庁webサイト「印紙税の手引き(平成29年5月)」
要は、受け取った金額や目的がわかる内容のものであれば、領収書として機能するとあります。
例えば、ノートの切れ端に、誰が(宛名)、どこで(発行者)、いつ(日付)、いくらで(金額)、どんな目的で(但し書き)、などの情報が記載されていれば、綺麗な領収書フォーマットでなくても、受取の事実が証明されるものであれば、領収書としての存在は担保されるということ。
では、次に領収書の場合、いくらの収入印紙を貼ればよいのか、見ていきましょう。
領収書の印紙代一覧表
記載された受取金額が
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
参考)国税庁webサイト「7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
いよいよ本題!収入印紙を貼らなくてもいい領収書の話。
5万円未満の領収書は収入印紙が不要!
これは、多くの人が知っている事実ですが、おさらいがてら。
以下のような文書は非課税文書とみなされるので、印紙税を払わなくてよいので、収入印紙を貼る必要がありません。
・記載金額が5万円未満(※1)の受取書(領収書含む)
・営業に関しない受取書(非営利に関するものや、医師や士業の作成する受取書も含まれます)
※1 平成26年3月31日までに作成されたものは3万円未満のものが非課税でした。
「5万円未満の領収書は収入印紙を貼らなくていい」という認識の方が多いと思いますが、上記の条件に文書が該当するため、収入印紙を貼る必要がないのです。
詳しく説明を知りたい方は、国税庁webサイト「印紙税の手引き(平成29年5月)」の「金銭または有価証券の受取書(第17号文書」部分を参照ください。
領収書を電子データで交付すれば収入印紙代が不要!
ここからが本題。
印紙税は「課税文書」に対してかかる税金であるため、
メールやFAXなどの電子データで作成された電子データに対しては課税されないとされています。
電子データは文書ではないから、課税文書には含まれずに非課税、ということです。
「たしかに電子データは文書じゃないけど、それ本当?」
と思わず言ってしまう内容ですが、
国税庁のwebサイトに事例とともに、「請求書や領収書をFAXや電子メールで提出する場合には、実際に文書が交付されないため、課税文書は存在しないこととなり、印紙税の課税原因はない。」としっかり記載があります。
「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。」
引用)国税庁webサイト
国税庁webサイトでばっちり説明されています。
つまり、本来収入印紙を貼らないといけない、印刷された請求書、領収書、契約書などの課税文書を、
PDFなどの電子データで発行してメールで相手に送付すれば、収入印紙を貼る必要がない(課税文書ではないから!)ということ!
印紙税について、電子データの龍証書は非課税について、詳しく確認したい方は
これまで説明してきた内容を詳しく確認したい方は、
以下リンク先の国税庁webサイトをご確認ください、
というのと、
それでもやはり心配な場合や、この文書の電子データの場合も適用されるのか、といった場合などは、税理士に確認や、管轄の税務署に電話などで問い合わせをすると確実でしょう。
<参考リンク>
・国税庁webサイト「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」
・国税庁webサイト「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について>(別紙)」
・国税庁webサイト「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」
・国税庁webサイト「印紙税の手引き(平成29年5月)」
・国税庁webサイト「印紙税」
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した「領収書を電子データで発行して収入印紙を貼らなくて済む方法」、実際の仕事では、お客様ありきの課税文書のやりとりのため、結局は、説明したとしても「紙で領収書がないと不安」「会社で紙の領収書じゃないとダメって決められているから」などの昔ながらの商慣習を優先しないといけないケースも多いと思います。
理解してくれそうなお客様には説明して電子データでやりとりをする、といった形が現実的かもしれません。
飲食店などの実店舗の場合だったら、従来のPOSレジだと、「5万円以上の支払いで領収書はメールで送ります」とかオペレーション的に現実的ではありませんが、
最近増えてきている、スマホやタブレットがカード決済できる「Square」のようなカードリーダータイプのレジを導入すれば、端末に入力してもらったメールアドレスに領収書データをメールして収入印紙を貼らずに取引完了、といった方法はありだと思います。
領収書などの電子データ作成においての注意点&おすすめな方法
領収書などの電子データ作成は、Excelやwordなどのテンプレートを使って作成する方法もありますが、
国税庁webサイト「電子帳簿保存法について」の中で記載がありますが、電子書類の場合、いつ作成されたものかわかるように「タイムスタンプ」が重要です。
タイムスタンプの正確性、セキュリティ面やデータ保存の信頼性など、総合して考えると、Excelなどで作って自分のPCのローカルデータで保存しておく方法ではなく、以下のようなクラウドwebサービス内で電子データを作成する方が安心感があると思います。
領収書などの電子データ作成には、電子書類作成webサービスの「マネーフォワードクラウド請求書」や「Misoca(ミソカ)
」といったサービスを使うと書類の管理やPDF作成、メール送付まで一貫して簡単にできるので活用されるのがおすすめです。
今回の情報がお役に立てたら幸いです!
以上、「みんな知ってた?領収書は電子データやFAXで作成すれば収入印紙を貼らなくてもOKという驚愕の事実!」でした!
それではまた!